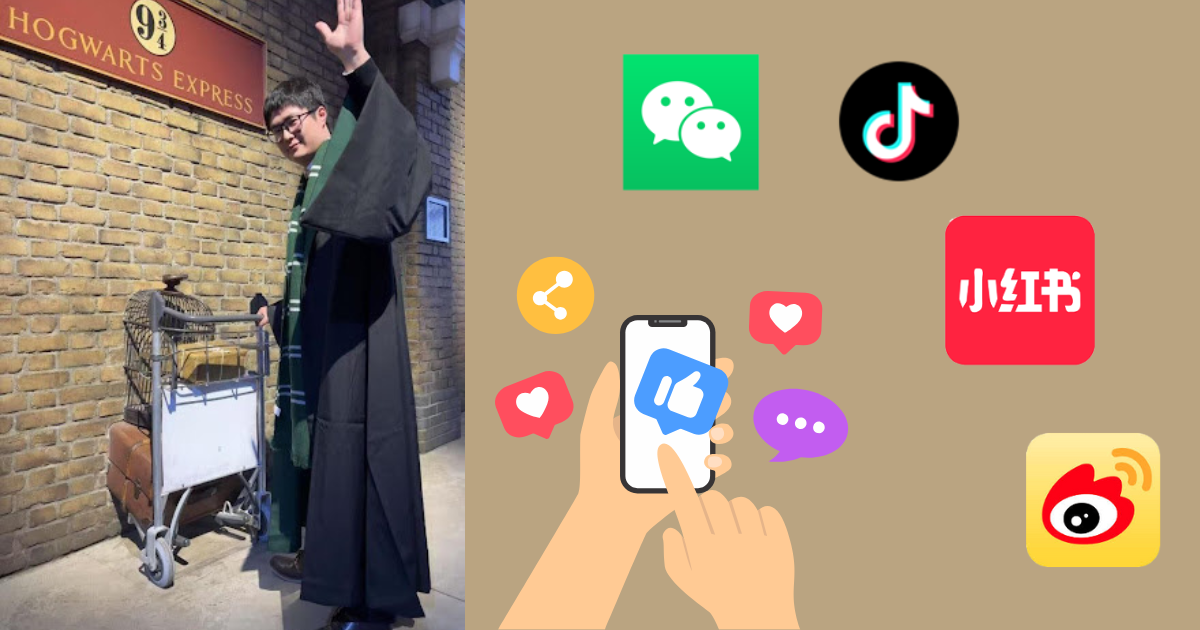コロナ禍が収束した2023年初頭、日中の入国規制が緩和されたため、3年ぶりにやっと故郷に戻ることができました。
「三年だけだから、中国社会は大した変化はないだろう」と思いながら、再び大陸に踏み込みました。
テーブルに貼られるQRコードを読み込みセルフ注文するレストラン、
商品バーコードをスキャンしキャッシュレス決済するコンビニ、SNS友達登録したら大額割引券がもらうカフェ、
大きなQRコードを手に持っている物乞いなど…私はまるで現代にタイムリープしてきた石器時代の人類のようで、ショックを受けました。
中国社会は自粛政策の中でデジタル化社会への進化を成し遂げていました。
このデジタル化社会を支え、今後もさらに活躍するテクノロジーの1つとしてSNSが挙げられますが、
SNSは現在の中国社会にどのような影響を与えているのでしょうか?
本記事では、日本に8年間住んでいる外国人留学生が中国におけるSNSの活用法をマーケティングの観点からご紹介します。
1.中国SNSとその特徴
中国社会において人気なSNSとそれら主要な機能を紹介します。
「中国で一番流行っているSNSは何?」と中国人に聞くと、「WeChat」以外を答える人はいないでしょう。
Tencent会社の目玉商品として、WeChat は2011年にリリースしてから、14年が経過し、
現在14億弱のユーザーを持っており、名実ともに中国の国民的SNSになりました。
WeChatの基本機能は、多くの日本人が使っている「LINE」のように、ユーザーに、
文字、音声メッセージ、画像やスタンプによるコミュニケーションの場を提供するプラットフォームです。
昨今世界中で話題となっている動画に特化したSNS「TikTok」は、中国企業のByteDanceが2016年にリリースしました。
中国の法律や規制によって、国際版は「TikTok」、中国版は「抖音」として、別々で運営されています。
内容は多少違いがあると思いますが、コアとなる短い動画で情報を伝達する表現方法は同じです。
中国のモバイルインターネット市場に特化したビッグデータ分析プラットフォームQuestMobileの調査によると、
2025年3月に「抖音」のユーザー数は10億を超えました。
アメリカのTikTok利用禁止法律の影響で、中国版のInstagramといわれるSNS「rednote」が注目を集めています。
前述したTikTokと異なって、「rednote」は中国版と国際版を分けずに運営しています。
そのため、海外から直接中国ユーザーの発信が見ることができます。
2013年に作られた「rednote」は、現在ユーザー数が3億を超えており、そのうち30歳以下の若者利用者が約85%を占めています。
またユーザーの男女比が3:7と、女性ユーザーが多いことも大きな特徴です。
中国で最も歴史のあるSNSは何かと聞かれたら、恐らく「Weibo」でしょう。
2007年頃流行していたTwitter(現「X」)の影響で、SINA(新浪)社は2009年に、
Twitterと似たようなメッセージ機能、プライベートメッセージ機能、コメント機能、
返信機能が実装されたSNS「Weibo」を公開しました。
「Weibo」は歴史あるSNSとして、新しいSNSにユーザーが奪われることもありますが、
2024年12月時点でユーザー数は依然5.9億を保っています。
| 名称 | 特徴的な機能 | ターゲット層 |
| ・即時通信機能(文字メッセージ、音声メッセージ、電話とテレビ電話) ・タイムライム機能(登録した友人だけが見える動画、画像、テキストの投稿。 「いいね」とコメント機能付き) ・バーコード決済機能 |
中国人をユーザーとして網羅しようとしている | |
Tiktok |
・ショートムービー投稿機能(基本5分以下の動画、1分以下の動画が多い)。 ・「いいね」、「コメント」、「コレクション」、「シェア」、DM機能付き |
短い時間をつぶし、情報を深掘りしたくない人 ※日本と異なり、中国のtiktokは、中年層や高齢層にも普通に使われている |
rednot |
・動画、画像とテキスト投稿機能(動画投稿の場合、基本10分以下、 5分以下の動画が多い。画像投稿の場合、基本20枚以下)。 ・「タグ」、「いいね」、「コメント」、「コレクション」、「シェア」、DM機能付き |
最初はファッション趣味の若年女性、現在は若者 |
| ・動画、画像とテキスト投稿機能(テキストは長文可能、最長中国漢字2000字。 動画投稿の場合、基本1分以下。) ・「@」機能(投稿に「@+ユーザー名」を入れると、当投稿が公開される際に、 @されたユーザーに特別通知メッセージを送る) ・「タグ」、「いいね」、「コメント」、「コレクション」、「シェア」、DM機能付き |
「タグ」機能の最初使用アプリであり、特定分野の情報を広く知る人。 ※ただ、現在は芸能界に関する情報がメインとなっている |
2.中国人ユーザーの関心
いくつかのSNSを紹介しましたが、中国人ユーザーにはどのような情報発信が受け入れられやすいのでしょうか?
筆者の視点でいくつか特徴を紹介します。
2-1.【格差問題】
どのSNSでも、やはり「格差問題」を言及するとアクセス数やコメント数が多くなります。
2021年、中国政府は中国全土で極度の「貧困」は解消されたと発表しましたが、
「先進地域」と「先進ではない地域」間の格差は依然として存在しており、対立も存在しています。
また、「経済格差」だけでなく、価値観の違いで生じた格差も議論になりやすいと思います。
例えば、親子価値観の格差を具体化した事例は、「結婚・出産」問題です。
少子高齢化問題は、現在中国においても社会問題になっています。
「生育は一族を継続させる義務だ」と主張する親と「競争で精一杯だったので、子を産んでもいい生活を提供できない」
と主張する子の間に、深いギャップが生じています。
このような経済格差や価値観ギャップへの関心は、実際にSNSマーケティングにも利用されています。
ここでは価値観ギャップを利用したSNSマーケティング戦略の例を紹介します。
中国では「剩女(sheng nü)」と呼ばれる、30歳以上未婚女性への偏見が根強く、
20代半ばを過ぎても独身でいると、『売れ残り』『親不孝者』と周囲から言われ、非常に肩身の狭い思いをします。
このような価値観ギャップに果敢に切り込んだのはスキンケアブランドSK IIです。
SK IIは「Change Destiny」を掲げ、両親の期待や世間の圧力に逆らう女性たちの声をSNSに投稿し、議論を喚起しました。
中でも「Marriage Market Takeover」という動画では、「20代後半独身女性=売れ残り」とされる文化の中、
「結婚しなくても人生は輝く」というメッセージを伝えています。
結果として、SNS上で大きな話題となり、Weiboなどでの拡散に成功し、社会常識に挑戦するブランド姿勢が共感を呼びました。
このプロモーションは自社ブランドを、価値観ギャップという社会課題を抱えた中国市場に当てはめた良い例と言えるでしょう。
上記のような「経済格差」や「価値観格差」を言及する内容は、中国人ユーザーに響くと思います。
2-2.【見知らぬ世界】
アクセス数の高いテーマとして、見知らぬ世界を見せることが挙げられます。
例えば、留学生が、「日本」、「生活」、「実態」などのタグを付けてSNSを投稿すると、
街歩きで撮った街並みの写真でも、電車から撮った沿線田舎風景のビデオでも、アクセス数やコメントは殺到すると思います。
農耕民族であった中華民族のDNAに刻んでいるライフスタイルは「安定」、すなわち定住して暮らすことです。
多くの人は、毎日変わらない街並みや景色を面し、生活を送らざるを得ません。
見知らぬ世界に関する情報が流してくれると、自然に見てしまうのでしょう。
実際に日本在住の中国人留学生が上記のような投稿をしており、日本文化への実体験の情報源として支持され、
旅行や生活関連ブランドのプロモーション案件へと発展しています。
現在Weiboフォロワー数は500万以上で、インフルエンサーとして活動しています。
また有名ブランドであるLouis Vuittonは、秦皇島Aranya(アランヤ)で3日間の体験型イベントを開催しました。
このイベントはただのファッションショーではなく、参加者が時間と空間を共有できる「フェス」形式であり、
ラグジュアリーな非日常的体験を提供しました。
このイベントは、WeiboやWeChatなど8プラットフォームでライブ配信され、中華圏での総視聴数は約2億7,000万に達しました。
結果的に高級ブランドと中国市場の接続を強化することに成功し、
Louis Vuittonは非日常体験を通じてブランド認知・好感度ともに大幅に強化されました。
3.中国人ユーザーの反感
投稿の内容によって、好き嫌いがあるのは当然ですが多くの人の反感を買う内容があります。
SNSを用いて企業活動を行う時はぜひ注意してほしいです。
【爹味(Die Wei)】
最近、中国のネット用語で「爹味(Die Wei)」という言葉が流行っています。
直訳すると「父親の味」という意味で、父親のような上から目線で説教する態度を指します。
これは性別に限らず、相手の状況や気持ちを考えることなく、自分の価値観によって一方的なアドバイスをすることを指しており、
そういった場合には「爹味」だと批判されがちです。
例えば、「価値観ギャップ」部分で紹介したような「若者は子を産むべきだ」とか、
「女は料理を作らないとダメだ」とか、中国文脈でのネタ「男は170センチがないと障害だ」なども、「爹味」の代表的な例です。
世界的な家具メーカーIKEAが過去に中国で放送したCMが騒動になったことがあります。
CMでは、とある家庭で「彼氏を家に連れて来られないなら、もう『ママ』と呼ばないで」と発言するシーンがあり、
多くの中国人女性が「シングル女性に対する侮蔑だ」「性差別的だ」とWeibo(微博)で激しく批判しました。
アドバイスを出す際に、相手側に立つという意識はかなり大事だと思います。
4.おわりに
今回は中国におけるマーケティングについて筆者の視点を交えながらご紹介しました。
中国で使用されているSNSツールや、ポジティブな反応を得られる投稿、
逆に反感を買う可能性のある投稿などについて紹介しました。
中国の市場は巨大であり、チャンスがあると同時にデリケートでもあります。
本記事が中国でのマーケティングのヒントになれば幸いです。
また、マーケティングだけに限らず、SNSは私たちの生活における重要なツールになっています。
AI技術の発展や少子高齢化の影響によって、中国だけでなく世界各国でSNSの役割は今後さらに重要になってくると思います。
私たちのようないわゆる「Z世代」の中国人は、デジタルツールやSNSとともに成長してきたと言っても過言ではなく、
上世代よりデジタルツールやSNS への親和性が高いという自信はもちろんあります。
SNSが利用できないと、まるで新しい時代に適応できない旧式の機械のように、絶好のビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。
本記事が、読者の方々の有益な情報になることを祈っています。
王 子常(WANG ZICHANG)
中国浙江省出身。龍谷大学政策学研究科博士課程に在籍中。
若年層における環境意識の日中比較をテーマとして研究を行う。
日中比較を通して、若者の社会意識構造を解明し、日中の若者の環境問題/社会問題に対する関心度を高められる適切な政策を打ち出すことが必要であると考えている。
日中の学術交流に報告者や通訳者として参加。
環境問題のみならず、日中の友好的な交流の架け橋となることを目指す。