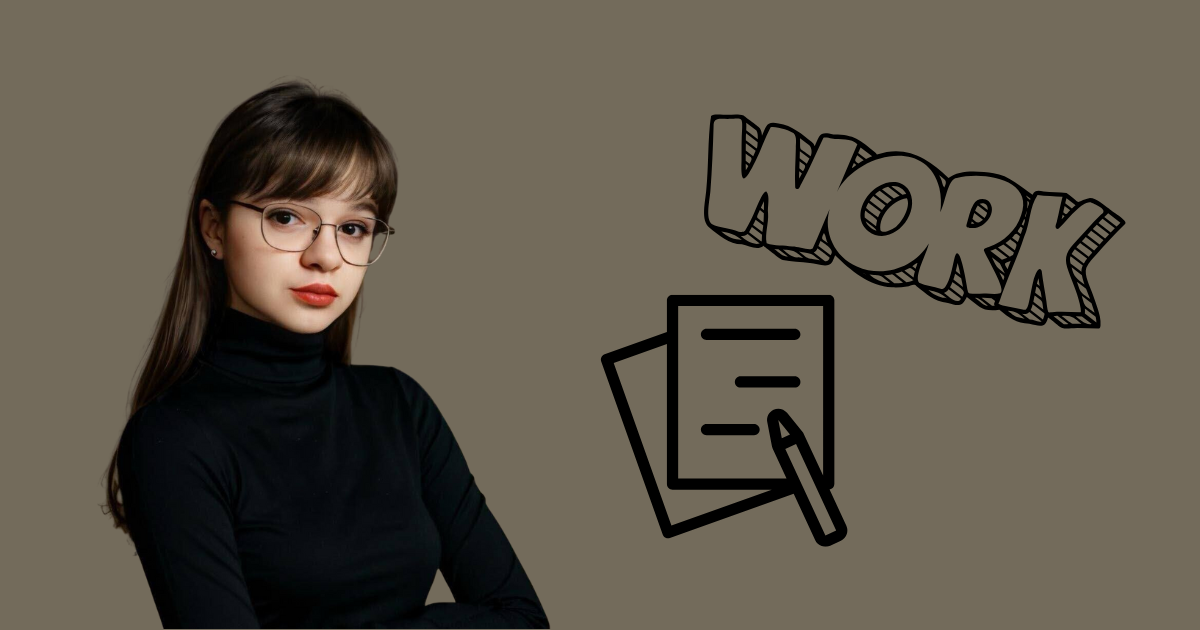日本の労働文化は伝統的な価値観、細部への厳格な配慮、チームワークの重視というユニークな組み合わせによって世界の注目を集めており、
世界的に認知されたブランド、技術革新、模範的なサービス水準を生み出してきました。
しかし、日本のビジネスパーソンが海外のパートナーと協力する際、文化の違いが双方に混乱や誤解を生むこともあります。
急速にグローバル化する昨今、文化の違いを理解することは、海外での成功を目指す会社や個人にとって必要不可欠なことです。
この記事では日本のワークスタイルの特徴に着目し、
海外のワークスタイルと比較することで異なる文化的背景を持つビジネスパーソンが一緒に仕事をする際に役立つ情報を紹介します。
1. 集団主義と個人主義
日本と海外(特に欧米諸国)のワークスタイルの違いの1つは集団主義が重視されているか否かです。
まず日本企業は個人の利益よりも集団の利益を優先し、調和を重視してきました。
そのため仕事を進めるプロセスにおいて、重要な決定が行われる前に、全員が意見を述べる機会を確保する傾向があり、これは団結力の向上に役立ち、対立を防ぐことができます。
このようにチームワークは企業生活の中核をなすものになっています。
プロジェクトの成功や失敗は、特定の個人に責任を負わせるのではなく、チーム全体で共有するのが一般的です。
チームメンバーはしばしば強い忠誠心を示し、個人的な成果よりもチームの成果を優先して、結束することがあります。
しかしながら、これらは一体感を育む一方で、時には個人の功績を曖昧にしたり、目立つ行動を妨げることもあります。
その結果、意思決定の遅延を招いたり、個人の創造性を奪う可能性もあります。
一方で海外の多くの国では、個人主義が一般的です。
完全に個人に着目しているわけではなく、チームの協力と個人の表彰の両方が推奨されており、
特に優秀な成績を収めた社員には表彰や昇進など目に見える形で報酬が与えられます。
そのため、各個人のスキル、業績、願望が前面に押し出されることが多く、個人の野心や主体性がイノベーションの原動力になると考えられています。
社員は自分の才能が認められていないと思えば、上司に異議を唱えたり、急進的なアイデアを提案したり、別の会社にチャンスを求めたりすることもあります。
このような方法は同僚間の競争力を高め、イノベーションを促進する可能性がある一方で、
よりストレスの多い、ライバル同士のピリついた雰囲気を生み出すリスクもあります。
チームとしての成果と個人的な成果のバランスを取ることは、異文化間のコラボレーションにおいて繰り返し議論されるテーマです。
日本のビジネスパーソンは個人的な賞賛よりもグループとしての成功を優先し、海外のビジネスパーソンはより競争的で成果主義的な環境を好むことが多いです。
2.肩書と実力主義
日本では海外と比べて、年齢・性別・職歴などが会社内での立場や人間関係に影響を及ぼします。
先輩・後輩の関係は、日本文化の特徴であると言えます。
職場における先輩とは、後輩を指導する年長者のことであり、後輩は先輩からのサポートを受け、それに敬意と感謝を示します。
このシステムは、チームメンバーの忠誠心、長期的な職場での絆、明確な責任感を育むことができます。
日本の多くの組織では、新入社員が何十年も同じ会社に勤め、こうした上下関係の絆を維持することがよくあります。
このような文化の背景には年功序列という考え方が存在します。
日本では一般的に、年上の社員はより大きな尊敬を集め、純粋に業績によってではなく、年齢や勤続年数によってより大きな決定権を持つことがあります。
これは実力主義的なシステムであればすぐに出世できるような、若くて高い業績を上げている人物のキャリアアップを制限することもあります。
また日本は性別の考え方も特徴的です。日本企業では女性は結婚や出産を機に退職するという伝統的な考え方がありました。
昨今、政府や民間企業は働く母親を支援し、男女平等を促進するための施策(産前産後休暇の延長や子育て支援制度の改善など)を導入していますが、
女性の労働参加や上級管理職への登用という点においては、日本はまだ多くの欧米諸国に遅れをとっている状態です。
対照的に海外の職場はフラットな組織構造を採用していることが多いです。
若手社員は先輩社員に対して気軽にファーストネームで呼びかけることができ、昇進も実力主義であることが多いです。
メンターは確かに存在しますが、その関係性は日本の先輩・後輩と比較すると、より柔軟で堅苦しくない関係性であることが多いです。
また評価に関しても、実力が重視されることが多いです。
年齢や勤続年数に関係なく、優秀であれば急速に昇進する可能性がありますし、このようなスピード出世は、年功序列に慣れている日本人は驚くでしょう。
そしてそれは性別についても同様で、多くの欧米企業ではジェンダー平等の取り組みによって女性のリーダー的役割が常態化しており、
必要なスキルと実績を示せば、昇進や重責を担う上で年齢が障壁になることはあまりありません。
よって海外のビジネスパーソンの中には、日本における年齢や性別の上下関係の意味を誤解し、年上の人物に適切な敬意を払わない可能性もあります。
3. 終身雇用と流動的キャリアパス
先述した1.や2.に密接に結びついているのが、終身雇用の概念です。
近年、経済的な問題により一般的ではなくなりましたが、新卒を採用して定年まで雇用するという概念は、未だに日本の多くの大企業に影響を及ぼしています。
終身雇用の概念を持った日本のビジネスパーソンは、会社が長期的な 「家族」のような存在であるという感覚から、
海外と比べて重労働や厳しい状況に耐える傾向が強いのかもしれません。
海外のビジネスパーソンは、1社に長く勤めるよりも異なる企業や業界を渡り歩くことが多く、それを自分のキャリアにおける一連の戦略的なルートだと考えています。
そのため、野心的なビジネスパーソンは、給与を上げたり、新しいスキルを身につけたり、異なる業界を開拓するために転職することが一般的です。
海外企業は成果に重点を置いているため、従業員との生涯にわたる繋がりは想定しておらず、パフォーマンスの低下に対して寛容ではないと考えられます。
結果的に、ダイナミックな労働市場が形成される一方で、職場においてやや取引的な考え方が助長される可能性もあります。
これはビジネスパーソンとしての継続的な成長を促し、変化を加速させます。
一方、日本企業で見られるような結束力や組織への忠誠心は低くなり、離職率も高くなる傾向にあります。
4. 意思決定 全体調和とスピード重視
日本企業では、「根回し」と呼ばれる意思決定の方法が存在します。
これは上層部に何かを提案する前に、担当者やチームが主要な関係者に対して密かに内容を共有し、非公式に意見を求める行為です。
提案が上層部の耳に入る頃には、関係者のほとんどがすでにその案に同意している状態となっています。
これは、1.で述べたように和を重んじる日本風土が反映されたものであると考えられます。
しかし、「根回し」をするには時間がかかり、特に根回しに不慣れな人にとっては不可解なことが多く、受け入れ難い風習である場合もあります。
一方で海外の多くの企業では、意思決定はより直接的で、迅速に行われることが多いです。
マネジャーやプロジェクトリーダーは、関係者のフィードバックを検討することはあっても、最終的な意思決定は、自らの権限によって独断で行うことが多いです。
この方法は、より早く結果を出すことができ、テクノロジー分野、マーケティング分野のような動きの速い業界では特に有効的な手段であると言えます。
しかし、日本のような多くの関係者を巻き込んだ協議を回避することは、
従業員に疎外感を与えることにもなりかねず、従業員の不満につながる可能性があります。
5. コミュニケーションスタイル 間接的or直接的
日本におけるコミュニケーションは間接的であることが多いです。
人間関係の悪化を避けるため、批判や意見の相違は曖昧な言葉で表現したり、微妙なニュアンスで伝えられることもあります。
また非言語的な行為として「空気を読む」と呼ばれるものがあります。
日本社会において空気を読むことは必要不可欠なスキルであり、重要な役割を果たします。
礼儀正しさ、グループの調和、すべての関係者の面目を保つことが最も重要であり、
オープンな衝突はチームの結束を損なうと見なされることがあるので注意が必要です。
海外では、直接的なコミュニケーションが重視されることが多いです。
フィードバックは明確であり、従業員は公の場であっても対照的な意見や考えを述べることがあります。
このようなコミュニケーションは問題解決を早め、積極的な意見交換を促しますが、日本の常識に慣れた人にとっては、
ぞんざいに扱われたと感じたり、過度に対立的であると感じられることもあります。
よって直接的なコミュニケーションを好む海外のビジネスパーソンが、間接的なコミュニケーションを好む日本のビジネスパーソンに対して、
率直に返答をする、もしくは率直な返答を期待すると、誤解を生んでしまう可能性があります。
6. ワークライフバランス
日本のワークスタイルは残業の文化でよく知られています。
一部の企業では、従業員が遅くまで残業するのは仕事量が多いからだけでなく、上司が帰るまで残っていなければならないという暗黙のルールに基づいている場合があります。
ワークライフバランスを改善することを目的とした政府の取り組みや企業改革のおかげで、
この慣習は改善の兆しをみせており、プレミアムフライデーやノー残業デーのような取り組みにより、
月に一度は定時退社が推奨され、残業を制限したり、リモートワークを推進する企業も増えてきています。
海外では、私生活の優先順位がより高くなっています。
自らのタスクを終えていれば、定時退社は普通ですし、西欧諸国では有給休暇やプライベートの充実が重視されています。
これらは従業員満足度を高め、仕事におけるストレスや疲労を抑制します。
しかしながら、日本人が外国人を献身的でないと感じたり、外国人が日本人を働き過ぎと感じたりすることもあり、
文化の違いが関係性を悪化させてしまう可能性もあります。
7. まとめ
日本人と外国人が一緒に仕事をする場合、これまでに述べてきた日本と海外の働き方のギャップが障壁となることがあります。
例えば、意思決定において、外国人は日本のプロセスを遅いと感じ、日本人は海外の意思決定を唐突だと感じたり、
コンセンサスが得られないと感じたりすることがあります。
コミュニケーションスタイルの違いについても、日本の間接的なコミュニケーションが伝わらなかったり、
海外の直接的な意見が過度に厳しいと思われたりして、誤解につながる可能性があります。
また立場上の後輩もしくは部下にあたる外国人が年上の日本人マネジャーに率直な意見をぶつけたりして、
知らないうちに礼儀作法に反している場合もあるでしょう。
このように日本独特のビジネスにおける文化が衝突を生むこともあります。
しかし、こうした摩擦はイノベーションのチャンスでもあります。
例えば、日本のチーム全体における合意形成と海外の効率性を組み合わせることで、思慮深さと機敏さのバランスが取れた構造を生み出すことが可能です。
また日本人の丁寧で慎重なコミュニケーションは、海外の明確で分かりやすいアプローチから恩恵を受け、相互に理解を深めることができると思います。
さらに先輩・後輩制度は、海外のフラットなスタイルと効果的に融合させることで、
献身的なサポートとリスペクトおよび個人成果主義によるスピード出世の両立を可能にするかもしれません。
XKulaの海外と日本の職場規範の概要が示唆するように、ギャップを埋めるには、お互いの習慣や期待に対する理解が必要となります。
有能な女性や若手社員を評価し、サポートする日本企業は、イノベーターを多く育てることに成功するかもしれません。
一方、日本の年功序列構造の違いを理解することを学んだ外国人は、チームとより強い信頼関係を築くことができると思います。
お互いの強みとリスクを尊重し、理解することで日本人と海外のビジネスパーソンは文化の壁を越えて組織を発展させる可能性を秘めています。
コラボレーションを成功させるには、オープンな対話を行い、文化的なニュアンスの違いを理解することが重要です。
日本のビジネスパーソンは根回しの重要性を明確にし、根回しがいかに結束力を高め、十分な情報に基づいた意思決定を促すかを理解してもらう必要があります。
一方、海外のビジネスパーソンは、特に動きの速い市場において、直接的な議論や迅速な意思決定がなぜ価値があるのかを理解してもらうことが重要です。
お互いの文化における基本的なビジネスエチケットを学ぼうとする姿勢は、日本と海外がコラボレーションするために必要不可欠なものになります。
セミナー、メンターシップ・プログラム、言語サポートなど、異文化トレーニングを積極的に推奨している企業では、統合がスムーズに進むことが多いです。
リモートワークやフレックス制を取り入れるなど、ある程度の柔軟性を持つことで、多様な従業員の期待に応えることができます。
また、定期的なフィードバックを取り入れることで、些細な勘違いや揉め事が大きな対立に発展する前に、速やかに対処することができます。
8.最後に
日本の独特な労働文化は、何世紀にもわたる歴史と伝統的な規範を反映し、現代のビジネスシーンにも影響を与え続けています。
深く根付いた先輩・後輩の上下関係や終身雇用の概念から、意思決定や間接的なコミュニケーションに至るまで、
こうした文化は強い一体感と組織への忠誠心をもたらしていると考えられます。
一方、海外のワークスタイルでは、個人の成果、柔軟なキャリアパス、直接的なコミュニケーション、意思決定のスピードが重視されることが多いです。
このような違いは摩擦を生むこともありますが、双方が尊重し合い、情報交換を行うことで相互成長の機会にもなり得ます。
海外に目を向ける日本企業にとって、海外の文化を意識することはこれまでの固まった概念を再考する良い機会になると思います。
そして最終的には、お互いの文化的背景を理解して尊重することで、
両者の長所を生かしたグローバルで、革新的かつ柔軟性のある理想的な職場を構築することができると思います。
これからあなたが海外で仕事をしたり、日本にいながら外国人と仕事をする際は、ぜひこの記事を参考にしてみて下さい。
ウクライナ出身。
国際大学大学院の修士課程に在学中で専攻は国際関係学。
ウクライナのカトリック大学では社会学を専攻。
研究テーマは紛争解決、人道的外交、国際関係で、特にグローバルな政策が地域社会にどのような影響を与えるかに着目している。
学業以外にも人道的な活動としてNGOである「Helping to Leave」で助成金制度のコーディネーターや日本関連の業務を務め、
戦争で被害を受けた人々の避難と医療の支援を行っている。
またScruples ResearchのQuantitative Researcherとして、国際的な安全保障や政治動向に関するデータ分析も行っている。
将来は、危機対策、人権、紛争調停を中心とした国際機関への貢献を目指している。
趣味は語学の勉強(日本語と韓国語、オランダ語を勉強中)、歴史と地政学についての読書、
世界のサイバーセキュリティ問題とウクライナの政治に関する分析記事の執筆を行っている。

翻訳/編集:株式会社hupodea 事務局